こんにちは。折々の時折のたけです。
農地付き空き家を申し込んでから半年、やっとのことで不動産登記書を入手することができました。内心ほっとしてます。
この登記書を手に入れるまで、法律的にはとても中途半端な状態で、元所有者の方や農業委員会の意向次第では全て白紙に戻ってしまう状態だったので、大丈夫だとは聞いていたのですが、内心ドキドキしながら話を進めていました。
今回は、その辺の話を書いてみようと思います。
なんでドキドキしていたのか?
「自宅からすぐのところにエディブルガーデン用の自分の農地があること。」にとてもこだわりが強かったのです。
「自分の農地」というのは、自分が思い描くエディブルガーデンを作るのに最低7年〜10年かかると考えていましたので、その期間内で「農地を借りて、所有者の意向で返却しなければならない可能性」を排除することを意味しています。
なので、今回取得した農地付き空き家の農地部分について、元所有者の方や地域の農業委員会の意向次第では法律的に「自分の農地」にすることができなかった場合に、そもそもの契約自体を無効にすることを私のほうからの条件として契約手続きをしてきました。
実際に、申込時に列挙されていた農地の一部は所有者さんの意向で最終的な売却のリストから外れています。(事前に事情を聞いていたので、とりわけトラブルというわけではありません)
あとは、農業委員会と一言で言っても、本当にその地域の自治体に判断基準が委ねられているので、登記書を手にするまでは、縁もゆかりもない土地の会ったこともない農業委員会の方々がどのように判断するのか?はこちらでは全くわからない状態でした。そんな中、他の自治体の農業委員会での農地付き空き家の購入条件の但し書きみたいな話を聞いていたので、リスクとしてはゼロとは判断し難い状態でした。(とある地域の農地付き空き家の場合、下限面積は1アールに下げるけれども、家庭菜園というのは認めません的な話とか・・・)
経緯
まずは経緯です。(物件探しや下見などの経緯はこちら)
- (2021年11月)農地付き空き家の買付証明書の提出
- (2021年12月)農業委員会へ申請する(1月審議分は12月15日〆切)
- (2022年1月)農業委員会の定例会議にて審査される(結果OK)
- (2022年1月末)不動産の契約書に押印して進める
- (2022年2月)住居の建物が未登記であることが判明して手続きを進める
- (2022年2月)リフォーム再見積もり、リフォーム申し込み
- (2022年3月)元所有者の方の書類準備に時間を要する
- (2022年3月)リフォーム完了&引越し
- (2022年4月)登記完了&登記書入手
1月の農業委員会の承認がおりるまで止めていた大きな事項が4つあります。
- 不動産契約
- リフォーム
- 引越し
- 自動車購入
承認OKがでた時点でそれらを同時に進めています。もちろん、元所有者の方には了承を取った上でリフォームなどを進めています。
同時に進めているのには理由がありました。
- 東京から1300km遠距離であるため何度も行き来するのが大変だったこと
- 住んでみないと実際の問題がみえてこないことだらけだったこと
- これ以上の事前検討は妄想だらけで無駄だと感じていたこと
- もとより長期間かかるエディブルガーデン構想着手に今シーズンを棒に振る可能性があったこと(本来は2月に着手したかった)
全ては2022年4月にエディブルガーデン開発の着手をするため、無理は承知で事前の準備は勢いでなんとかしようと考えました。
大変だったポイント
農業委員会の承認がおりるまで
農業委員会の承認がおりるまでは、契約が白紙になり物件探しからやり直す必要があったので、本当にドキドキしてました。
そして、エディブルガーデンへの歩みを止める気もサラサラなかったので、万が一承認が降りなかった場合に備えたバックアッププランとして、農地付き空き家の探し直しに加えて、地域おこし協力隊への応募も準備していました。
地域おこし協力隊への応募については、その地域での深いコネクション作りにとても有効ですので、エディブルガーデンへの道筋としては、空き家バンクを利用した農地付き空き家の取得とは全くの別ラインとして有効だと判断してました。
登記書を持たないままでのリフォーム
リフォームにはそれなりの時間がかかります。また、コロナの影響で資材の入手に時間がかかるという話も出ていました。
2022年4月にエディブルガーデン開発に着手するためには、登記書の入手を待ってる余裕はありませんでしたので、元所有者の方の了承を取った上で、リフォームを進めました。その後、お相手の気が変わるリスクもありますが、その辺はこちらの意思を明確に示して後には引かないと相手に伝わればという考えもあり、リスクテイクしました。ただし、リフォームは最低限住めるだけの範囲です。
それでも、登記書を手にするまでは、ドキドキしてました(笑)
農地を取得する覚悟
さて、農地を取得したら、いくつかの義務やルールが発生しますので、その取得するにはそれなりの覚悟が必要です。
農地とは固定資産である
農地は、いうまでもなく固定資産です。なので、農地にかかる固定資産税を毎年払わなければなりません。また、農地を勝手に農地以外の用途にすることも法律上で禁止されています。農地の転用には、法律に基づいた上で最終的に農業委員会の許可が必要となります。
農地を適切に管理する義務
農地を取得すると、農地を適切に管理する義務が発生します。何をもって適切か?というのはその地域地域で微妙に違うようですが、基本的には耕作または草刈りしなさいと言われるようです。
うちの地域のケースとして、草刈りの理由としては、イノシシなど害獣やスズメバチなど害虫の棲家とならないようにということでした。
ルールを守らないと農業委員会からの指導がはいるようです。
遠隔に住んでいたり、自分で草刈りするのが叶わない地主さん向けの有料の草刈りサービスなるものがあるようです。
農地のコンディション
あと、正直いいまして、もし、農地のコンディション(立地や広さや形状や土質など)が良ければ、近所の農家さんが買ってると思います。売る方も空き家にタダでついているような値段で売るわけもないと考えたほうが得策だと思います。面積が小さすぎたり、不便過ぎたり、水捌けが微妙だったりすることもあるでしょう。
なので、農地付き空き家についている農地のコンディションは購入するときによく検討したほうがいいです。

私の取得した農地も、里山の中で水が引かれていない元水田の棚田みたいになっている複数の区画の一部です。まわりの土地も近所の人が家庭菜園に使っていたり、草を刈って管理はするけれども耕作していない土地がほとんどです。おそらく、作業効率の関係上で、本格的に営農するための条件としてはよいものではないと思われます。
おわりに
以上が、私が農地付き空き家を取得した体験談です。
世の中には、私のように農地付きを条件として空き家を探している人もおられると思います。
他の方のブログなんかをみていると、もっと早く処理している方もいらっしゃるみたいですが、私は後半追い込みをかけて半年でした。
取得するまでは、取得できるのか?とドキドキしながら進めてましたし、いざ取得してみると気に入らなくとも簡単に売り買いできないし、持っているだけで義務が発生する、それが農地なので、取得するには色々と覚悟も必要だと思います。
ちなみに、私は土地の水捌けや日当たりから時間をかけて整備する過程も楽しむつもりでこの土地を買いました。なので、深く大きな穴を掘って地層を確認したり、スコップで水路を整備して雨降りの中で水の流れを確認したり、そんなことも楽しくやってます。
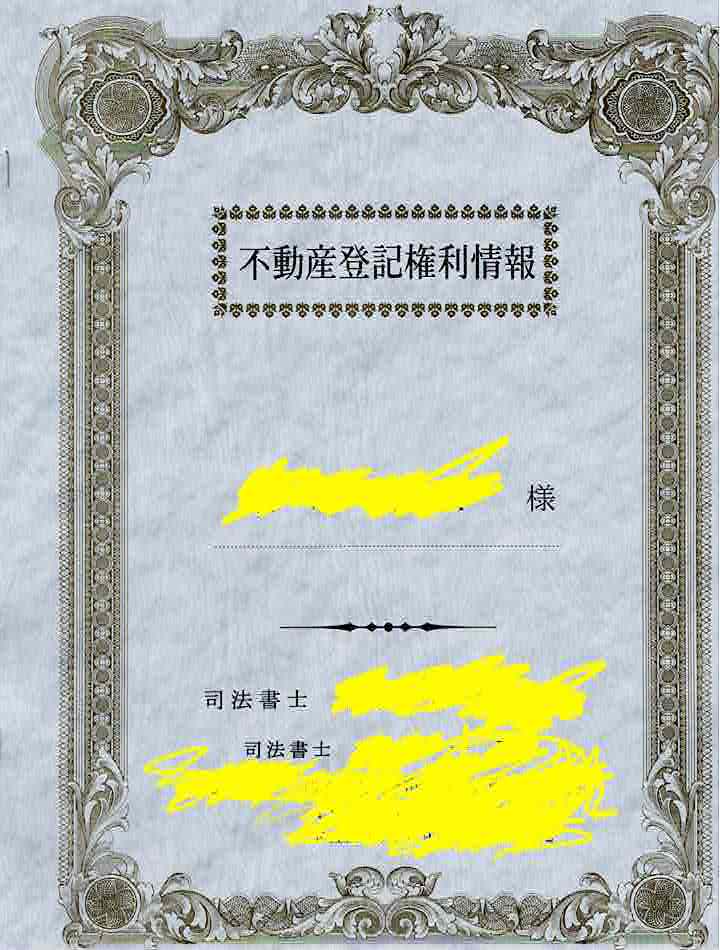


コメント